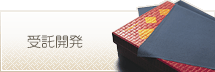|
抹茶(まっちゃ)は緑茶の一種。茶道で用いられるほか、和菓子、かき氷、アイスクリーム、チョコレート、料理の素材などとして広く用いられる。 抹茶は、有態に言えばチャノキの葉(茶の葉)を粉末としたものだが、その製造工程が煎茶とは異なり、蒸してから乾燥させ、これを砕いて葉脈などの不純物を取り除き、さらに茶臼という臼でひいたものである。江戸時代までは茶臼でひきたてのものを飲用していた。茶道では前日などに茶臼でひいたものを飲む。家庭用にはすでに粉末化されプラスチックのフィルム袋に密閉されたものが販売されている。変質を避けるため開封後は密閉容器に入れ冷暗所に保存する。その種類には、黒味を帯びた濃緑色の濃茶(こいちゃ)と鮮やかな青緑色の薄茶(うすちゃ)がある。飲料として飲む場合は、濃茶は茶杓に山3杯を1人分として、たっぷりの抹茶に少量の湯を注ぎ、ポタージュスープより少しゆるい程度のとろりとした入れ方をする。従って「濃茶を練る」という。薄茶は茶杓1杯半を1人分として、多目の湯で入れる。 この飲料としての抹茶を茶筅(攪拌するための竹製で専用の道具)で撹拌する際に、茶道の流派によって泡の立てかたが異なる。千家は、表千家はうっすらと泡が立つ程度、裏千家はたっぷりと泡立てる。立てる泡がもっとも少ないのが武者小路千家などである。 抹茶の種類は高級品や一般向け製品の違いを別にすると単一である。甘みがより強く、渋み・苦味のより少ないものが良しとされ、高価である。一般に高級なものは濃茶に用いられるが、もちろん薄茶に用いてもよい。現在の茶道では、濃茶を「主」、薄茶を「副(そえ)」「略式」と捉えている。爽やかな苦味は砂糖の甘味と良く馴染み風味が際立つため、菓子の風味付けにも好まれ、抹茶味のアイスクリームは日本では定番風味の一つともなっており、日本アイスクリーム協会の調査では1999年から2007年まで、バニラ、チョコレートに次いで第三位の地位を占めている。 |
| 喫茶の風習は元々中国の唐代から宋代にかけて発展したものである。8世紀頃、中国の陸羽が著した『茶経』(ちゃきょう)には茶の効能や用法が詳しく記されているが、これは固形茶を粉末にして鍑(釜のこと)で煎じる団茶法であった。
抹茶(中国喫茶史では点茶法(てんちゃほう)と呼んでいる)の発生は、10世紀と考えられている。文献記録は宋時代に集中しており、蔡襄の『茶録』(1064)と徽宗の『大観茶論』(12世紀)などが有名であるが、これらの文献では龍鳳団茶に代表される高級な団茶を茶碾で粉末にしたものを用いており、団茶から抹茶が発生した経緯をよく表している。この抹茶を入れた碗に湯瓶から湯を注ぎ、茶筅で練るのが宋時代の点茶法であり、京都の建仁寺、鎌倉の円覚寺の四つ頭茶会はこの遺風を伝えている。 日本には平安時代初期に唐から喫茶法(おそらく団茶法)が伝えられたが、抹茶法が伝わったのは鎌倉時代とされる。 その伝来としては、臨済宗の開祖となる栄西禅師が1191年中国から帰国の折に茶種と作法を持ち帰り、その飲み方などが日本に広まったという説が有名である(詳しくは茶道の項を参照のこと)。 栄西の『喫茶養生記』には茶の種類や抹茶の製法、身体を壮健にする喫茶の効用が説かれている。建保2年(1214年)には源実朝に「茶徳を誉むる所の書」を献上したという。 日本の製法 収穫は1年に一度。若葉をていねいに手で摘む。手摘みした茶葉はその日のうちに蒸した後、揉捻(じゅうねん)を行わずに乾燥させる。もまないところが煎茶や玉露との大きな相違点である。この碾茶を刻み、葉柄、葉脈などを取り除いて真の葉の部分だけにし、粉末にする。温度変化の少ない石臼(茶臼)を用いる。 |
 |